さまざまのこと思い出す桜かな(Nostalgic Sakura)

高知工科大学キャンパスにて王碩玉先生と(2010年頃)
昨夜からの大雨で、今年の桜も終わった。今年はなぜか、季節を惜しむ気持ちが強く湧き起こる。
桜、桜、桜
・・・ さくら、さくら、さくら、
・・・・・・ サクラ、サクラ、サクラ
・・・・・・・・・ Sakura、Sakura、Sakura
「櫻」 ― 木偏に貝殻ふたつ、そして女。見事にその姿を表して、何とも美しい漢字である。
春の日本列島を覆い、これほど人の心をハラハラさせ、また多くの人を喜ばせる花(自然現象)が他にあるだろうか!!! そして、その引き際の何と、美しく潔いよいことか!
75年の人生で出会った桜たちが走馬灯のように脳裏を去来する。特にマレーシアから帰国後の勤務先ー東京八王子の大学セミナーハウス、香美市鏡野公園に隣接する高知工科大学、千鳥ヶ淵に近い大妻女子大学ーは何れも桜の名所だった。
さまざまの事おもひ出す桜かな (芭蕉)
やがて若葉に主役を譲り、桜はまた1年「忘れられて」しまう・・・。 季節は穀雨へと移り、私も10日後には76歳になる。数え年で喜寿である。来年は更に老いを深め、より美しい桜にまみえることができるだろうか。サクラよ、また来年! ・・・インシャーアッラー!




🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
あゝ、うるわしの日本
私は今、郷里の高知にいる。居間の簾越しに名残の桜がひらひらと散ってゆき、新緑が萌え始めて春の息吹を感じさせる。突然踊り出てくる白いモンシロチョウにも心が動く、明るい日本の春だ。
家のまわりの草取りを終えた母が、名も知らない白や黄色の草花を湯のみに差して、「はい、あなたにあげます!」と差し出した。洗濯物をかかえ、下駄をつっかけて裏庭に出ると、一面蕗が茂り、「十二単」という名の紫色の花がドクダミの陰で可憐に咲いていた。何とやさしい日本の春の風景なのだろう。
「今年の春は、どうしても桜を見たい。あの潔く散る姿を見たい!」
日本の春が近づくにつれ、マレーシアにあっても、そんな思いがつのって抑え難かった。その思いはどこかで半年前のあの悲しい出来事とつながっていた。私は弟の死というものをもう一度、桜と共に日本のやさしい自然の中で抱きしめたいと考えていたのかもしれない。
4月6日に帰国した私は東京に一週間滞在し、九段界隈の落花の雪の美しさを見届けて、京都・奈良経由で、久しぶりに汽車を乗り継いで帰郷した。
京都・賀茂川べりの桜は東京の桜に比べ、枝振りがのびやかで、レンギョウの黄や雪柳の白と和して、見事だった。いにしえの京の都に想いを馳せた。その後、奈良に向かい、神武天皇を祭った橿原神宮に寄り、飛鳥に辿り着いたのはもう夕暮れ近かった。
聖徳太子創建の橘寺の正門はもう閉まっていたが、門前の桜の木を見上げると、弟がアフリカで天に上った日と同じような蒼天が広がり、半透明の上弦の月が掛っていた。
高松塚古墳や天武・持統天皇陵などをまわって、日没は石舞台古墳を見下ろす丘の上で眺めた。満開の桜、ひんやりした静かな空気、鶯の鳴き声、空までが淡い桜色に染まり、さながら東山魁夷の絵のような美しさだった。西方浄土に向かって手を合わせると、哀しみの泉から一筋の涙がこぼれ、静かに頬を伝って流れた。
「春の野に霞たなびきうらがなしこの夕かげに鶯鳴くも」
母が手帳を開いて、大伴家持の歌を教えてくれた。
今回の小旅行は「外国で日本語や日本文学を教えていて『大和』という言葉を再発見した」と、熱っぽく報告した娘に、この機会に大和の地を踏ませてやりたいという母心が動いて実現したものだった。
翌日は神戸で母方の祖父母の墓参りもした。
僅か2日間に数え切れないほど乗換えをして、日本列島を南下した旅だったが、どこもかも桜が満開で、「自然のやさしい恵みを受けた麗しの日本」を今年ほど強く実感したことはなかった。(了)
私が口ずさむ桜の短歌
🌸 願はくば花の下にて春死なむ その如月の望月のころ(西行)
🌸 敷島の大和心を人問わば 朝日に匂う山桜花 (本居宣長)
🌸 世の中にたえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし(在原業平)
🌸 散ればこそいとど桜はめでたけれ うき世に何か久しかるべき(作者不明)
🌸 明日ありと思う心のあだ桜 夜半に嵐の吹かぬものかは(親鸞)

マレーシアにいた私に家族の花見便りが届いた(@九段下の土手)


大学セミナーハウスの枝垂れ桜

中嶋嶺雄理事長、職員の皆さんと

千鳥ヶ淵には季節になると朝な夕な足を運んだ

🌸リンク🌸
さくら葬
サクラ吹雪のサライの空へ・・・

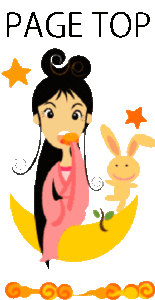




Comment from すみ子
時間 2025年5月3日 10:27 AM
季節は桜からツツジへと移りましたが、桜への私の想いもあり、遅くなりましたがコメントさせてください。
命日が、祖父は4月19日、父は4月22日ということもあり、県外の墓所にこの時期墓参をしていました。
愛媛県の冷涼な高原にある墓所は、この時期桜が満開で、私も美喜子さんのように西行のこの詩を心に浮かべていました。
願わくば花のころにて春死なむ その如月の望月のころ
桜は華やかであり潔い。また来年・・・。