朝ドラ『あんぱん』に見る食卓の風景(Changes in the dining style)

ご近所の玄関の青もみじ
NHK朝ドラの『アンパン』を毎日楽しみに見ている。好評だった一昨年の朝ドラ『らんまん』に続いて、今年も高知が舞台のドラマが毎朝、全国津々浦々の茶の間に放映されているのは「まっこと」(本当に)誇らしいことである。出演者が懸命(?)にマスターした土佐弁がいい感じで流れていて、ほっこりする。主人公の、のぶが「たまるか!(わぁ!)」を連発し、「いごっそう」「はちきん」「たっすい(がはいかん)」など、土佐人気質を知るキーワードも散りばめられていて、高知の文化も「こじゃんと」(うんと)紹介してくれている。
ところで、ある日の場面でのぶの実家朝田家の食卓が「銘々膳(箱膳?)」だったのに驚いた。一方、もう一人の主人公、崇の柳井家はテーブルに洋食!? 銘々膳の風景はその後何回も流れた。戦前、戦中は「ちゃぶ台」の時代ではなかったのかしら?などと時代考証に興味を持った。
大学セミナーハウスに勤めていた折に、「茶の歴史」の研究で有名な熊倉功夫先生を1泊2日のセミナーにお招きし、基調講演をしていただいたことがある。「日本の食卓の変遷」というタイトルだったことを思い出し、大学セミナーハウス・ニュースに掲載された原稿(要約)を読み返してみた。
日本の食卓は近代百年の間に「銘々膳」(箱膳)から「ちゃぶ台」、そして「ダイニング・テーブル」へと3種類も経験している、という生活文化、社会の変遷のお話である。
興味深い内容なので、是非ご一読ください。熊倉先生、その節は大変お世話になりました。
iush.jp 大学セミナーハウス⇒ 法人案内⇒ セミナーハウス・ニュース No.166
https://iush.jp/uploads/files/20220413140316.pdf
🍒 季節の花たち 🍒

散歩道


明治神宮(2024年)


庭の紫蘭と小夏


日比谷公園(2022年)


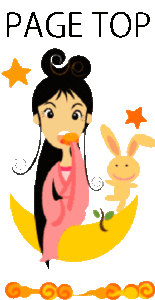




Comment from 中澤法子
時間 2025年5月27日 7:45 AM
私も『あんぱん』を観るのが日課となっております。やなせたかしさんが高知追手前高校の大先輩ということもありましょうか。父は、やなせさんの3歳下で学徒動員で海軍に招集され、復員後高知新聞社の記者に採用されましたが、直前に復員輸送艦勤務の命令が下り、やむなく記者を断念した経緯があります。同じ記者として遭遇したやもしれません。香美市にあるアンパンマンミュージアムを訪れた際、偶然にも息子とやなせさんが写真に残っています。30年前のことです。
「箱膳」もなつかしいです。小学生の頃、父の生家に行くと皆「箱膳」で食事をしていました。熊倉先生の文献にもあるように、食器は洗わずしまっており、子供心に不潔だなと思った記憶があります。60年ほど前のことでしょうか。「箱膳」は
今でも生家の蔵に保管されております。