明治の女―祖母よそい その4(A Story of my Grandma 4)

花
母は花が好きであった。今も母の声が花の中から聞こえて来るような気がする。いろいろな花を育て、自分も鑑賞し、仏前に供え、また床の間に生けた。時に珍しい花が咲くとお客を招いて共に楽しんでいた。特に春蘭、月下の美人、菊など見事に咲かせていたことを思い出す。
母が亡くなってからは、四季の花が不断の友となって私を励ましてくれていることをしみじみ感ずる。永い年月、私は花を生けてきたが、真白の花だけを生けたことはなかった。この間母の日に、初めてカーネーション、百合、バラすべてを白のみにして生けた。思いなしか厳粛で清楚で、これまでかつてなかった気持ちになった。
母の日よ清楚に匂う白き花
おそらく他の色の及びもつかぬ気高さを見たのであった。
私のようにいつも寝ている者にとっては、花を生けることも暇つぶしであるが、あんなに忙しかった母によくあの時間があった、と驚く他はない。しかも、種を蒔き、挿芽をし、肥料をやり、消毒をし、雨の日は雨をよけ、風の日は風を遮り、あのように世話をし、そして一枝、二枝を切って生ける。並大抵のことではない。父が花が好きで、よく花を作ったが、身体の不自由なままに、ほとんど母にやらせた。それが母をして、花を作るようにさせたかとも思われるが、動けぬ父の傍に鉢を持って行き「お父さん、こんなにきれいに咲いたよ。見てごらんなさい」と言って見せるのは父に対する心尽くしではあろうけれども、自分が好きでなければ出来ぬことであろうと思う。片岡の家の花に対する主体は、やはり母であった。父が「花を花を」と無理難題を言うことを「私より花が好きかね」と抵抗を示しながらも、実は自分自身が花と一つ心になっていた。
私が両親のもとに暫く滞在した時のことであった。ある夏の夜、月下の美人が開くと言うので、父と母と3人で、その開花を待った。父も母も比較的元気で、その晩の話題は忘れたが、長く座って待ったことがたまらなく懐かしい。恐らく花の開く音を聞き逃すまいと、3人は静かに静かに話したに違いない。今や母はすでになく、父も病床にある。ああ・・・。
次男の健次郎夫婦は未だ故郷にいる頃、よく祖父母の花づくりや、野菜づくりの手伝いしたものだ。母が亡くなった時の父への手紙を再録する。
秋を思わせるような冷たい雨の日、おばあさんは逝く。
夏の日の菊畑の想い出を残し、おばあさんは逝った。
小柄できれいな、漬物上手なおばあさんはもういない。
おじいさん、何と申し上げるべきか、言葉がありません。ありふれたお悔やみの言葉で慰めようもないおじいさんの心中を想い、ただそばで手を握って上げたい。ご自分が不自由なだけに思い切り泣けないのではないかと思い、余計に可愛そうです。気落ちするなと言っても無理なことでしょう。思い切り泣いてください。
明治の夫婦のあり方を示してくれたお二人に、僕は敬意を表していた。生きていくことの厳しさを含めて、お二人は夫婦の絆が如何に強いものであるかを教えてくれた。
( 中略)。
不器用な手で糞をこねるものだからバラバラになって、おばあさんが「おまさんはやりなさんな」と言っていたことを覚えている。庭仕事のあとのビールの美味しかったこと、日曜日は手伝いに行くのが楽しかった。今はそんなことを思い出します。
おじいさん、告別式には行けないので、母におじいさんの手を握ってもらいます。陽子の分と僕の分です。遥かにおばあさんのご冥福を祈らせていただきます。
これにもあるように、糞をこね、土を運び、肥料をやることで菊作りは容易ではなかった。菊作りで、父母はよく喧嘩をしたようであった。元来父は昔の役人肌が抜けず、命令的に人を動かそうとするので、母は抵抗した。自分が動かないで、口先の指揮、命令である。台風が近づく頃には、菊の枝も成長し大型の重い鉢を幾十も安全な場所に運び込まねばならない。晩年手足の不自由になった母はよくこぼしていた。しかし美しい花が咲けば、ケロリと忘れて喜ぶ母であった。菊が一輪、二輪花を開く頃になると、「お父さん大輪が咲いたよ」と顔をほころばす。そして、鉢を並べてお客を迎え、歓待したものだった。
夫は黄菊白菊の大輪のものより、道傍の野菊の方が美しいと言っていたが、それでも父母の菊作りの苦労には敬意を表していた。そしてこの頃は、私が四季折々の花に鋏を入れる様子を「母への慕情か」とじっと見ているのである。
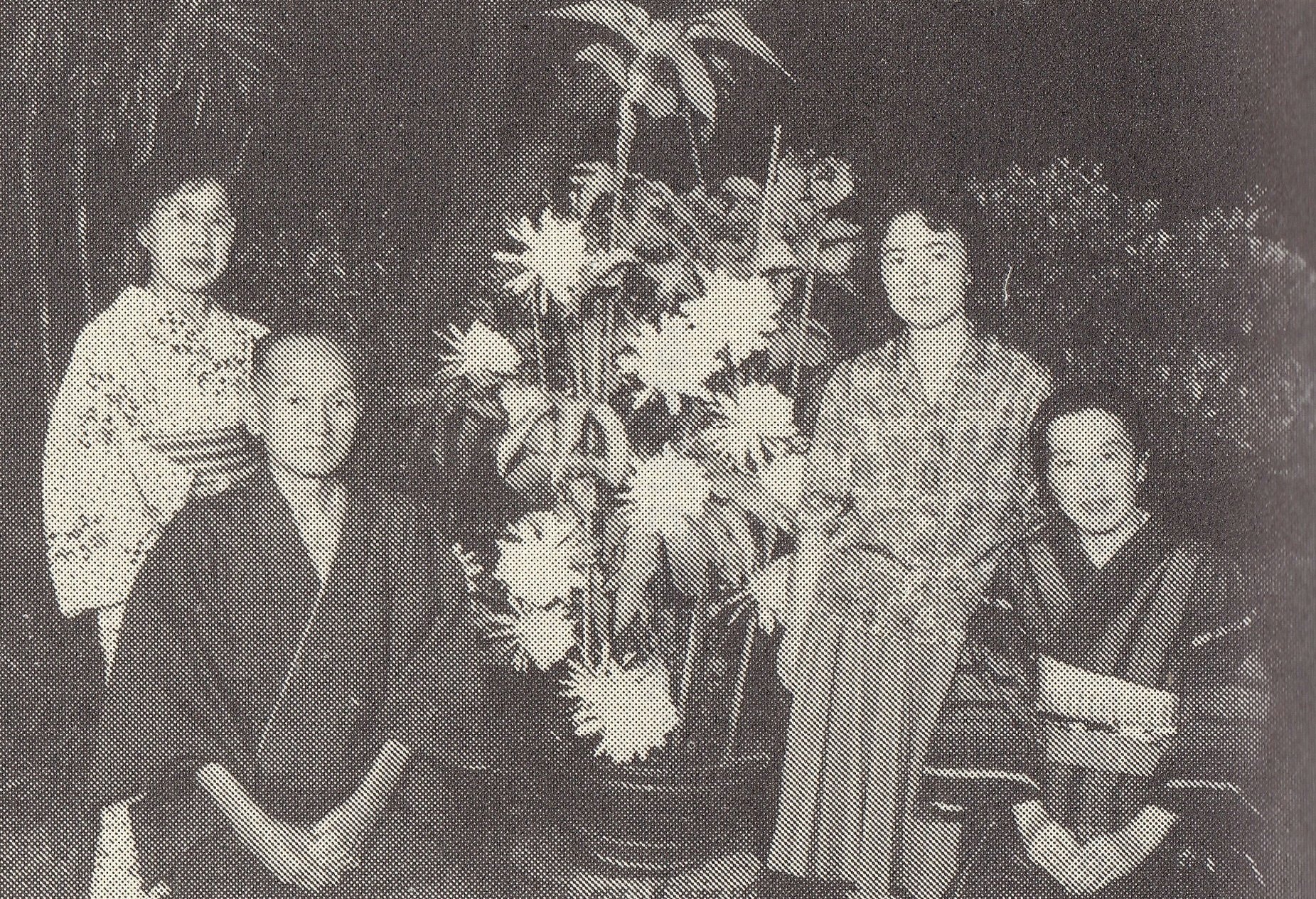
 月下の美人の開花を静かに待つ
月下の美人の開花を静かに待つ

 菊作りは晩年の祖父と祖母の生きがいであった
菊作りは晩年の祖父と祖母の生きがいであった





