土佐弁の力(The charm of Tosa dialect)

たっすいがはいかん!
朝ドラ『あんぱん』を見ていらっしゃる方々にはすっかり馴染みの土佐弁だと思います。主人公の柳井嵩はこれまで自身も認める「たっすい」男として描かれてきました。「たっすい」は人物の場合、弱々しい、頼りない、意気地なしなどといった意味です。ドラマでは作り手たちの遊び心からか「たっすい」が連発され、私も思わずニンマリしてしまいます。
さて、この「たっすい」が広まったのは、キリンの高知支店がラガービールのキャッチコピーとして使い始めてからかもしれません。もう30年近く前のことです。「(ビールはキレがなくちゃ)、気が抜けているようなのはダメ!」というわけです。上記写真は有名な観光スポット「ひろめ市」の入り口にかかっている広告ですが、居酒屋などでもよく見かけるポスターです。
前にも触れましたが、『あんぱん』は土佐弁を標準語とうまくバランスを取りながら効果的に使っています。「たまるか」、「こじゃんと」、「まっこと」、「ほいたらね」、などなど県外の方も覚えてくださったのではないでしょうか。
龍馬の「~ぜよ」はあまり聞かれず、「~ちゅう」、「~やき」、「~が」、などがよく使われています。唯一私が耳慣れなかったのは「~にゃあ」です。高知で育っておらず、「ネイティブ」でないからかもしれません。
土佐弁は好評で、県外の人からも「土佐弁ってかわいいね」などと言われるそうです。私はドラマの土佐弁を聞いて「心がぬっくう」(あったかく)なります。嵩の伯父寛の名セリフなど、土佐弁だからこそ、やさしく、深く心に響いてきたのではないでしょうか。その他、主人公ののぶはもちろん、釜じい、母親の波多子、妹の蘭子らの土佐弁も素晴らしいです!
ところで、私が一番好きな土佐弁は「ありがとう」(「とう」の語尾を強く言う)です。
2005年に高知新聞に連載をした「故郷で世界に生きる」の最後を次の文で締めくくっています。
「最後にもう一度お礼を申し上げたいのですが、私は土佐弁の「ありがとう」(「とう」の語尾を強く言う)の響きが大好きです。「ありがとう(「とう」にるびをふる)」と申し上げてお別れしたいと思います」
もう一つ、「みてる」という土佐弁。
「寿命が尽きる」という意味です。「満てる」という漢字から来ているのでしょうか。人生十分に満ちて全うしたという意味で、「天寿を全うする」と言い変えてもいいのかもしれまんが、「みてる」の方が気負わず、死をより穏やかに自然現象の一部として受け入れているような気がします。
『あんぱん』では、多くの人物の死が大切に描かれています。のぶの父親、妹蘭子の恋人豪、崇の伯父寛、弟千尋 友人岩男、のぶの夫次郎、そして先週はのぶの祖父釜じいが孫娘たちの歌う「よさこい節」の中で「みて」ました。釜じいの素晴らしいエンディングだったと思います。
私も釜じいのように「みてる」ことが出来たらいいなあ。
やがて死ぬ けしきは見えず 蝉の声 (松尾芭蕉)
やっと鳴き出した蝉の声に耳を傾けながら、この、昨年に負けぬ猛暑に耐えている76歳の老女であります。
8月3日 追記
先週の『アンパン』で釜じいに連れ添った”くらばあ”がのぶと崇の結婚を見届けた後、みて・ました。「ありが・と・う」と穏やかで美しい笑顔を残し、「ほいたらね」とー。
リンク:
🌻 朝ドラ『あんぱん』に見る食卓の風景
🌻 故郷で世界に生きる(高知新聞連載2005)
🌻 好きな言葉
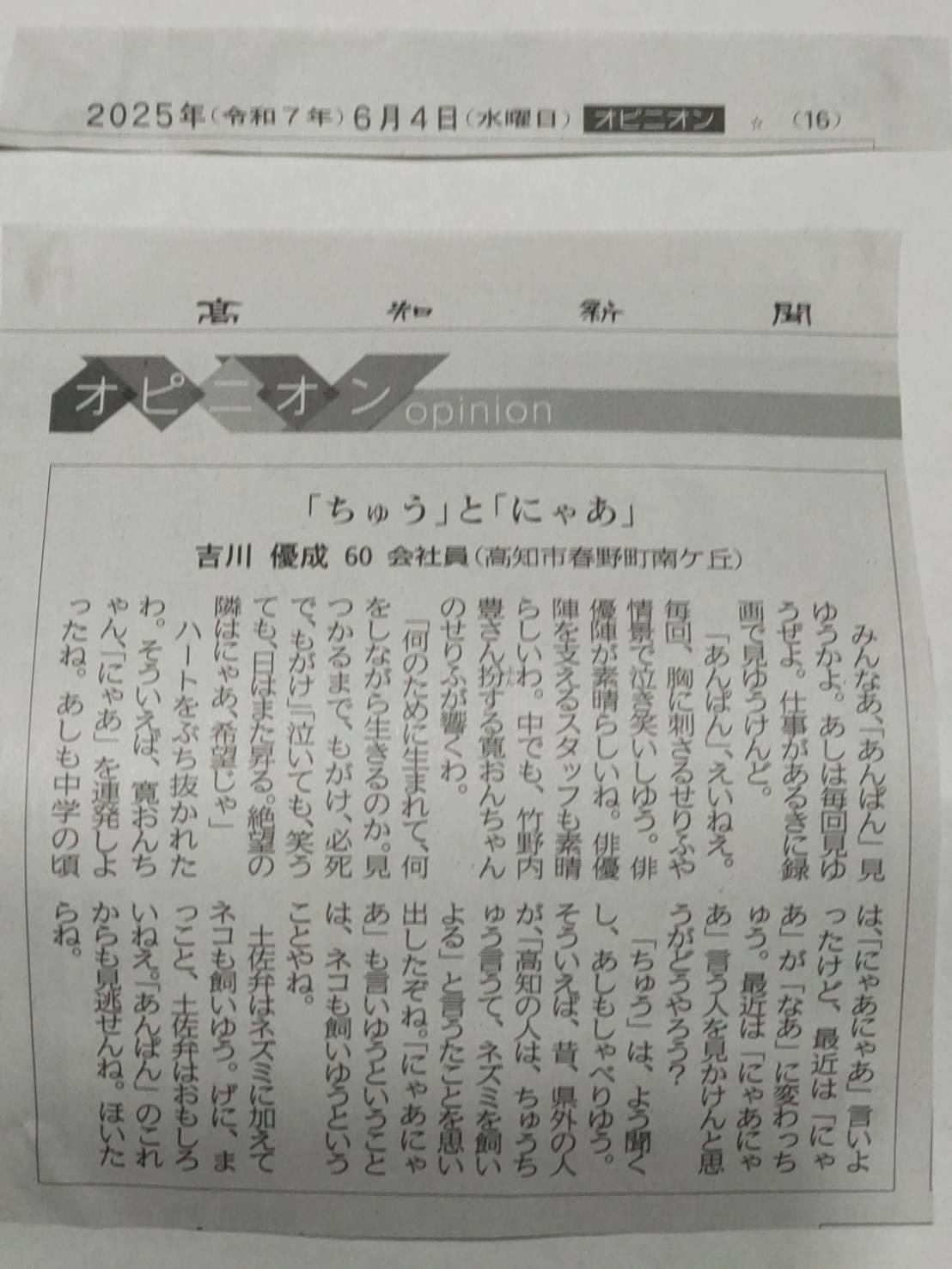
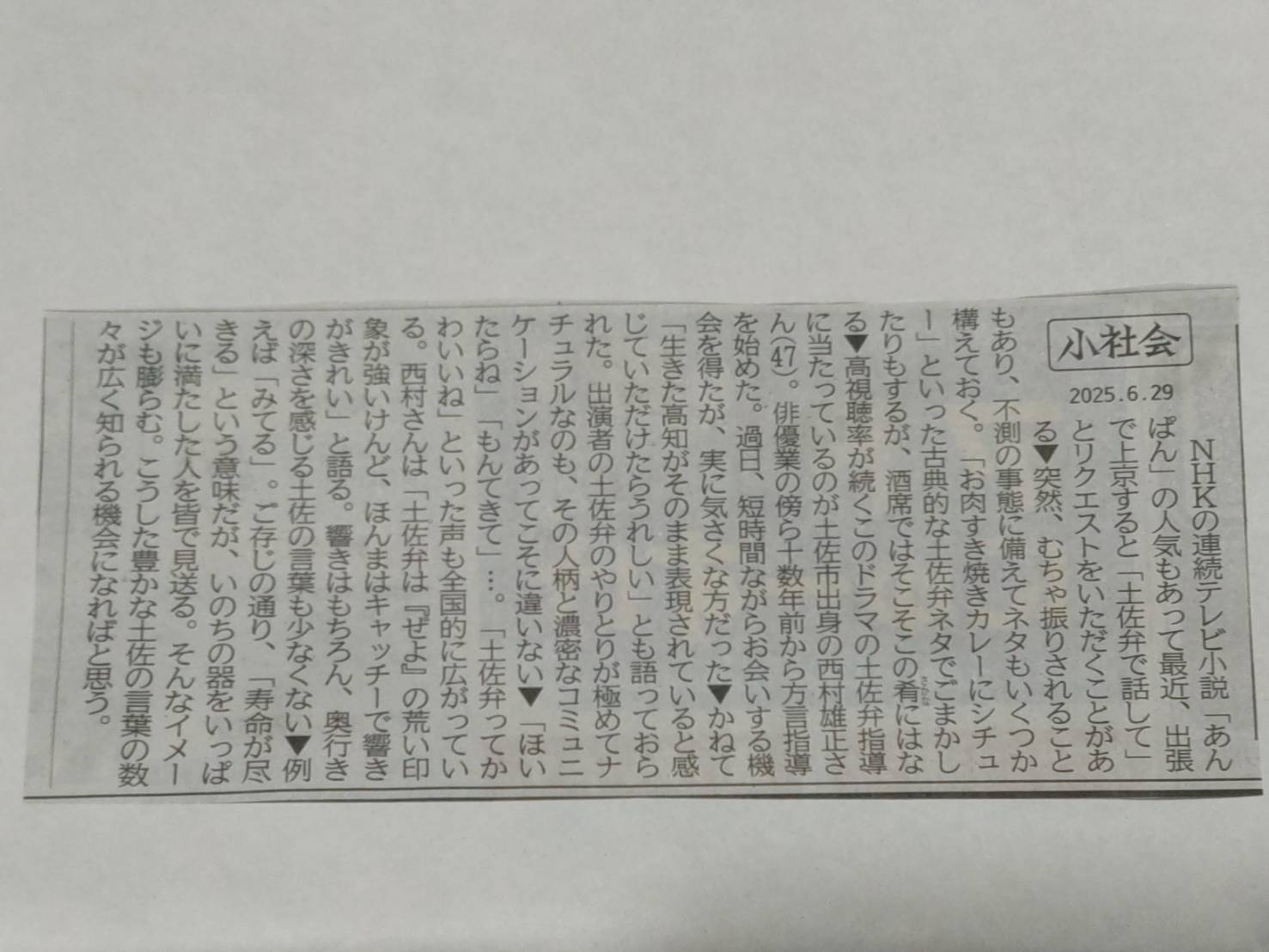

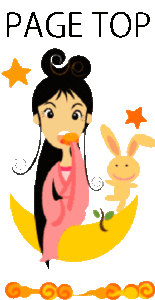




Comment from 伴 美喜子
時間 2025年8月27日 3:33 PM
「外語大ESS」の後輩、浅井稔さんより以下のコメントをいただきました。ありがとうございます!
...「土佐弁の力」も、とても「ほっこり」する文章で、心がほかほかになりました。ここのところずっと朝ドラ見ていないかったのですが、2012年の「梅ちゃん先生」以来初めて、13年ぶりに毎日「あんぱん」を見ています(笑)。やなせたかしさんの人生、ならびにアンパンマンという作品にはもともと大いなる敬意を頂いていたのですが、それに加えてドラマの随所に土佐弁が見事に散りばめられていて、この味は忘れられずにて毎回見てしまう、ということとなっております(笑)。私の田舎は愛知県の岡崎で、そこにも三河弁という方言があります。言葉は文化の最たるものにて、自分が生まれた場所の言葉を話せるというのは、これはもう一生の宝物です。そういう意味では、土佐弁は素晴らしい言葉だと感じ入っております!